 ── その三、おミキの恋は吹きさらし ── ★ Illustration Top:03 ★ 一
翌日、 王鳥まひるは校舎の屋上に立ち、横浜の町並を、ぼーっとながめていた。 手にはさっき、タコさんウィンナーと交換したたまご焼きが、 ものがもてる幻って便利だな……そう考えてから、まひるはたまご焼きを口にほうり込む。 あまーい味が広がった。 いまのまひるは まひるはゴミになった楊枝を弁当箱に入れると、ちらっと後ろに視線をむける。 そこには、さっきまで自分もいた、女子の仲良しグループが数人、きゃははと声を上げて笑っていた。 彼女達はもう、まひるを認識することはできない。 まひるはつい今しがた、彼女達を調節し、自分が初めからここにはいなかったと思うようにした。 実際今日は、一緒のお昼はキャンセルするつもりだったのだが、彼女達が屋上でランチするといいだしたため、やむなく昼食は一緒に食べて、途中で どうせ彼女達を調節しなければならないのなら、楽しくお弁当を食べてから…… 「たまご焼き、おいしかったよ」 おかずを交換したクラスメートにそっとつぶやいてから、まひるは視線を空にむける。 目線の座標設定を上昇させて、周囲の山々を越えた視界を得る。 晴天にもかかわらず、北のみなとみらい21地区をふくむ横浜駅周辺の青空は、灰色にくすんでいた。 西に目をこらせば、遠く富士山の輪郭も見てとれるが、台風の翌日など、よほど空気が澄んだ日でもなければ、霊峰がくっきり見えることはない。 もっとも、まひるが実際に見ていたそれは、数百メートルの上空に、さっきからじっとわだかまっている。 彼女にはそれが、 決して自分と一つにはならない力。 それを手中にすることが、最終的に《猫と狩人》が破滅を回避する唯一の手段であると、まひるは確信している。 この二ヶ月、できることならなんでもした。 あとは、自分を信じるしかない。 「うんっ」 大きくうなずいてから、まひるは視線を校舎裏がある真下に落とす。 どうやら、闘いが始まったようだ。 二
手に武器はなく、まったくの丸腰。ちなみに眼鏡はかけていない。 彼女の左側には廃材の山があり、さっきまで野良猫達が昼寝をしていたが、この場のただならぬ気配を察してか、いまは姿も気配もなく、しーんと静まりかえっている。 『校舎裏にて待つ。C∴A∴H』 すわんに宛てたメッセージは明確だった。 《C∴A∴H》とは、《猫と狩人》の洋名《 指定の場所をおとずれた、すわんの前に立ちはだかる《猫と狩人》は、彼女とおなじ二年の女子で、 まだ、獣の耳はなかったが、髪は金髪、どぎつい ただし、 凶器以外のなにものでもないそれを、 すわんの目から見ても、切っ先が微動だにしないところなど、絶対に素人のものではない。 「アンタ、自慢の剣はどうしたのさ?こっちゃあ、この 「そんなこと、あなたには……!?」 すわんがいい返そうとしたのを見計らい、 動きが早すぎて、すわんは目をつぶることもできない。 だから逆に、自分がどうなっているか、認識することができた。 ギンッと音をたてて、喉への打突は 二撃目の面はすわんの すわんの体の首、頭、左わき腹の三か所からは少し、蒸気が吹きだしており、痛いというより、むしろ熱い。 たまらず飛びのいた 尾は即座に、いびつだが鋭利な刃に硬化して、おれた刀身をおぎなう。 『バカもんっ!全部食らう奴があるか!』 すわんの脳裏に、ゲンガが罵声を飛ばす。 『んなこといったって、早すぎるよぉ』 動きはなんとか見えていたが、体が反応するヒマがない。 『ただの剣だから、その程度ですんだがな、今度の奴は刃にたっぷり そもそも、 あれからすわんは、鯖斗やゲンガから、必要最低限の説明しか受けていないので、実際どうなっているかよくわからないのだ。 『ま、そのうちどーにかなるかぁ』 うだうだ考えてもしょうがないので、すわんは頭を切りかえた。 いつのまにか、まひるが廃材の山に腰かけ、すわんと 『 すわんは右手を横に突き出して、心のなかで ドゴォーンという轟音が、すわんの左側から起こり、まひるが腰かけていた、廃材の山が吹き飛ぶ。 その爆心に、超級幻我が突き立っていた。 『……あれぇ?』 すわんは首をかしげる。本当なら、突き出した右手で、高度三百メートルで実体化し、加速落下して来る超級幻我をつかむはずだったのだ。 『ヘタクソ!』とゲンガ。 すわんは吹き飛んだ廃材のなかに、まひるの姿を探した。 すこし離れた場所に、まひるは何事もなく立っている。 「あーびっくりした!」 髪を掻き上げてから、ぽりぽりと頭をかく。 なまじすわんの心が読めるばかりに、虚をつかれたまひるではあるが、吹き飛び、校舎に叩きつけられそうになる寸前、座標設定を変更し、べつな場所に出現しなおしたのである。 「ほら、 まひるの言葉に、 を打ち込んで来る。すわんはそれを、かろうじて左に飛んでかわし、超級幻我をつかみ、引き抜いた。 すわんは一度、フーッと息を吐いてから、剣を頭上に掲げると、キメ いわく…… 『 「 浄気はすなわち その名も 口上と同時に、剣から莫大な量の蒸気が噴出する。その白煙を突き破り、蒸気たなびく剣をふりあげて、すわんは 視界のなかの 「 劇で身についた破邪の叫びとともに、すわんは思いきり、 その斬撃とまともに打ち合った 崩れ落ちる二つの塊に、振り抜いた刃から吹き出す大量の蒸気が流れ込み、それらが鈍い音とともに地面に触れるころには、周囲は白煙に満たされていた。 三
「ちはるお姉ちゃん!」 そう呼ばれて 昼休みも終わり近く。 相棒のすわんがいないので、教室で時間を持てあましていたミキに声をかけたのは、クラスメートの女子、 「な、なに?安寿?」 いきなりミョーな呼び方をされたので、動揺するミキ。 「すわの妹って、あんたのこと”ちはるお姉ちゃん”って呼ぶみたいじゃん……って、それはそうと、お客さんみたいよ、ちお」 ニヤニヤしながら、入口のほうを指さす安寿。 一般にミキは『ちお』と呼ばれることが多い。『おミキ』だの『ちはるお姉ちゃん』だのいう呼び方をするのは、王鳥姉妹だけである。別にそれがイヤなわけではないが、今のように、それをネタにからかわれることがある。 ……ま、いいけどねと思いながら入口を見ると、そこには 「谷々君……」 そうつぶやいたミキにはもう、周囲が見えていなかった。 見えていなかったから、気づかない。 廊下や隣のクラスから、なにやら異様などよめきが起こっていたことに。 鯖斗の用件は、すわんが今どこにいるか?というものだった。 すわんがらみ以外で鯖斗がこのクラスを訪れることはない。それはわかっていたことだが、ミキは失望を隠せない。 そんなミキの態度に、気づいた風もない鯖斗。 「う、うーん……すわだったらさっき、 ミキが親友の危機をこともなげに言ったのは、何も鯖斗に心を奪われていたからではなかった。 その意味に気づいた鯖斗は、静かに後ろに立つ人物に視線を向ける。 「!?……」 ようやくミキも気づいた。さっきから周囲の人間が、決してこちらに視線を合わせようとせず、だが確実にこちらを意識しているコトと、その理由に。 鯖斗の問いに、その少年、 「わかった。どうもありがとう、千春御さん」 鯖斗の挨拶を残して、谷々兄弟は去って行く。 ミキはそんな二人を、ただ引きつった笑顔で見送るしかなかった。 「樺良先輩って、登校拒否やめたのねぇ」 「そみたい、ねぇ」 いつの間にか脇に立つ安寿が、わずかに顔を赤らめながら、樺良の後ろ姿を見送っている。対するミキは、さきほどから呆然自失となったまま。 「ねえ、すわが呼び出し食らったって本当?」 「そういってたわ」 「それで止めようとは思わなかったの?」 ミキをのぞきこむように見る安寿。その瞳はかすかな期待に輝いている。 「なんで?」 それが当然であるように、ミキは答えた。 「ううん、おっけー、おーけー、何でもないよ、のーぷろぶれむアルヨッ」 何かに満足した安寿は、鼻歌まじりにスキップしながら、教室にもどって行く。 「……何だってのよ、一体?」 四
『よーするに、コワしっぱなしにできるのは、邪悪なトコロだけなんだ……』 たとえ体を両断しても、時間がたてばナシになるという、剣の設定通りの現象が、ついさっき、実際に彼女の前で起こった。 蒸気が晴れた後、すわんが斬った 狐の尾と耳はすでになく、あるのは無残に分断された女生徒の体……のはずなのだが、元に戻ることがわかっていたし、なぜか切断面からの流血もなかったので、残酷なことをしたという印象や実感が、まったくなかった。 それよりも、どうやって再生するのか興味があったので、彼女はじっと両断された体を見ていたのだが、いつまでたっても変化がない。 だがふと注意をそらし、視線を別な場所に向けてから戻すと、その瞬間を見計らったかのように、両断されたはずの肢体は、無傷の不良少女に変わっていた。 ひざまづいていた 手に超級幻我を持ったまま、すわんはじっと、 がなかったせいもあるが、もし正気にもどっていたとすれば、今までのコトはすっかり忘れているはずなので、うかつなことはしゃべれない。 どのみち、すわんは言葉をかけるつもりはなかった。 いたげにガンを飛ばしてから、ヨロヨロと校舎裏から立ち去って行く。 まひるの姿はすでになく、超級幻我が突き立った廃材の山も、いつのまにか元どおりになっていた。唯一の闘いの痕跡は、打ち捨てられた日本刀、三撃目にすわんの逆胴で へし折れた状態に再生した そんなこんなの闘いが終わっても、昼休みの終わりにはまだ間があったので、すわんは今、廃材の山に腰かけてボーッと時間をつぶしている。 超級幻我が壊したものは、いずれ復活するけど、《猫と狩人》が壊したものは壊れっぱなしなんだ……すわんがその効果を実感したころ、二つの人影が彼女に近づいて来た。 もちろんそれは、演劇部造形班主任、 五
「首尾はどうだった?」 「上々ですわ……」 すわんは笑ってそう、返事をしてから、さきほどの闘いのあらましを報告した。 鯖斗は黒ずんんだ革の手帳にメモを取りながら、その話 を聞いている。背後に立つ すわんも、あえて言及しなかった。 鯖斗はすわんの報告が完了してからも、しばらくメモになにやら書きつけていたが、やにわにパタリと手帳を閉じてすわんを見る。 「まず確認しときたいんだが……」 鯖斗はそう、切り出した。なにかしら?と目顔で問うすわんに鯖斗は続ける。 「 『はぁ?』 すわんは内心で肩透かしを食らいながら、鯖斗に聞き返した。 「ほかに方法がありますの?」 「昨日あれから、兄貴やゲンガに事情を聞いた。どちらも完全なものではなかったけど、おおよその事情はつかめた。それで、俺なりに状況を分析したんだが……」 そこまで話して予鈴が鳴った。あと五分で授業が始まる。 「……まあ、詳しい話は今度ゆっくりするとして、これに、今までの情報をまとめておいたから」 そういって、鯖斗はちょっとかさばる厚みのレポート用紙の束を差し出した。 表紙には、手書きの楷書で『《猫と狩人》およびその周辺の事象に関する考察』と書かれている。これだけの厚さのレポートを昨日一晩で書いたとすれば、徹夜したのはまず間違いないだろうが、いつもの 「これを読めば、 がわかるのかしら?」 「俺なりの解釈だけど、王鳥にもわかるように書いたつもりだ」 鯖斗は、さらりという。 『なんか、ミもフタもないいい方ねぇ……そのとーりだけどさぁ……』 「そう……ではありがたく、拝読させていただきますわ」 「ああ、それから……」 とってつけたように鯖斗がいった。レポート用紙をもって、教室にもどりかけていたすわんがふり向く。 「まだなにか?」 「さっきの話のつづきなんだが……もし王鳥が、その、本気で 「よろしいんじゃなくて?」 アッサリとした返事の、すわん。 「本当に、いいのか?信用できると思うのか?」 「……べつに信用などしてませんけど、まひるも谷々先輩のこと、眼中にないみたいでしたし。邪魔さえしないんだったら昼寝してても、協力しても私はいっこうに構いませんわ」 『へーん、いってやった!なまじゴネるより、こっちのほーがキクだろ!』 というすわんの内心を無視して──当然なのだが、最近この常識は崩れつつある──樺良は一歩前に出ていう。 「ほーお、チキューケナシザルのメスのくせに、『敵の敵は味方』、 僕も、四つ耳をのさばらせるぐらいなら、少しばかりチキューケナシザルを繁殖させとくのはなんでもない。ま、よろしくな」 「……」 トーソーのジョードーという耳慣れない言い回しが、正しい喧嘩の仕方という意味であることを理解するのに、しばらく時間がかかった。 『なっ……ぬぅあにぃぃ!』 反発するタイミングを逃したすわんを 追い打ちに鯖斗がいう。 「王鳥さあ……あと、そこに落ちてる もらっていいかなぁ?」 日本刀は、刃物としての美しさが芸術的価値をもつ、世界でも珍しい刀剣である。鯖斗としては、もとから日本刀には興味があったし、折れているとはいえ、あれほどの刀がぞんざいに打ち捨てられているのは、造形屋として我慢ならなかっただけなのだが、結果としてすわんをイラつかせる結果となった。 それでも彼女はつとめて、平静に返答する努力をした。 「谷々の好きにすればいーじゃん。わたしには、関係ないもん!」 鯖斗は若干いぶかしげな顔をしたが、そのままいそいそと刀を拾いに行く。 すわんは自分が、内心をそのまま言葉にしてしまったことに、まったく気づいていなかった。 当然ながら、鯖斗が続けて「あ、それから昨日の制服は、ちゃんと処分しておいてくれよ」といったことも聞いていなかった。 かくてすわんと鯖斗は、校舎裏で始業のチャイムを聞く 六
夕刻、横浜市中区 典型的な日本家屋の六畳間の中央で、すわんとまひるはちゃぶ台を囲んで正座し、夕食を食べていた。メニューは焼魚におひたし、ごはんに味噌汁、お新香。 きわめて まひるは帰ってきてからずっと、何やらむずかしい顔で、考えごとをしていた。 今も、うわの空で焼魚の小骨を皿に並べている。 そんなまひるを、すわんはごはんが半分ほど残ったお茶碗を左手でもって、右手の箸先を口元に留めながら横目でうかがっていた。 そんな二人に、台所ほうから声がかかる。 「どうした、二人とも。ケンカでもしたのかな?」 それは、台所の 浅黒い肌に、いかにもスポーツマンという顔立ちと体格。千春御ミキの密かな分析によれば、王鳥姉妹が 「ううん、なんでもないよ、パパ」 先に応えたのはまひるであった。 すわんも一歩遅れて、お茶碗を置きながら応える。 「ええ、そうですわお父さま」 「そうかい……」 すわんの物言いに、わずかに苦笑する父。 よく誤解されることだが、すわんはいわゆる『良家のお嬢様』ではない。父の飛翔は物流業、母のあずさは建築業という、共働き夫婦である。二人とも、とりたてて高貴な出身ではなかったので、当然すわんも普通の娘として育てられるはずだった。 実際にすわんをあの物腰に躾けたのは、父方の祖母の王鳥 それとて 「ひしょくぅ~ん、すわちゃぁ~ん、まぃるちゃぁ~ん、ちょっとちょっと、きてみてぇ~」 その妙なテンポの呼び声は、三人がなんとなく黙り込んでいたのを見計らったかのようにかけられた。 声の主が母あずさのものであることは、ここにいる三人には当然のこと。 「はやく、はやくぅ~おっもしろいよぉ~」 浴室からくるらしいその声に、三人は顔を見合わせた。 そして、誰とはなしに浴室へ向かう。まひると飛翔はなぜか両手にそれぞれ、お箸と焼き魚の皿、おたまとフライ返しを持っている。すわんもなんとなく、二人をまねて手近にあるテレビとクーラーのリモコンを持って後に続く。 一同が浴室につくと母あずさが、脱衣所に設置された洗濯機の前でうれしそうにぱたぱた手を振っている。 「みてこれ、みてこれ、みてこれぇ!」 そういって、洗濯機の中を指さすあずさ。 三人が中をのぞき込むと、そこではコマ切れになった無数の布切れが、渦の中を豪快にまわっている。 「ねね、すごいでしょ、素敵でしょお~?」 アニメキャラクターのプリントされたエプロン(クレヨンなんたらいうらしい)をかけた母あずさは、とても二児の母というか、成人した女性には見えない。すわんは『 「あれ、これうちのガッコの制服だよ」 まひるがそう、指摘する。いわれて見れば、たしかに 「そ~なのよぉ~。すわちゃんとまぃるちゃの服を洗濯してたら、こーなっちゃってぇ~」 あずさは、口元のホクロを右手の小指でぽりぽりと掻きながら、うれしそうに『こまったわ~』という表情をする。 「あ゛……」 そこまできて、すわんはやっと思い出した。昨日、 本来、超級幻我の能力を正しく発動できれば、すわんおよびすわん周辺の物体は浄気によって保護されるはずだし、事実今日の戦闘では服に傷など一切ない。 確かに昨日のすわんには、ぶっつけで戦闘しなければならなかったというハンデがあり、能力を完璧に使えずに服を痛めてしまったのは仕方がない面もある。だが、その後のフォローを鯖斗に指示されながら(昼休みにも念をおされていたのだが、聞いちゃいない)、それを実行することすら念頭になかったのは、明らかにすわんのミスである。 『おねーちゃあん……うちでケンカはしない約束でしょ。こーゆーのは、パパやママに見つからないよーにして欲しいなぁ』 まひるはこちらに視線を向けず、心に直接、抗議してきた。 『ううう……すまないです、わ』 あやまるしかない、すわん。さりげなく、世界制服を策謀する悪の秘密結社の首領に説教される正義のヒロインの図、だったりする。 『とりあえず、約束があるから記憶は操作しないけど、うまくゴマ化しといてね』 『しょ、そんなぁ(しょげなぁ)~』 その物体が、断片化したすわんの制服であるということがはっきりすると、両親は追求をすわんにしぼった。嫌疑の晴れたまひるは、父親に書斎のパソコンを使用することを告げると、難しい顔のまま、お箸と焼き魚を持って浴室から姿を消した。 「すわちゃ~ん、怒んないから~、なぁんでこ~なったか説明してねぇ~」 声は怒っているが、目が笑っているあずさ。 「あずさと同意見。どーやったら、こんなになるんだ?」 おたまとフライ返しをにぎったまま、ずずいと近寄る飛翔。 「え、えと、ですから……」 汗かきベソかき後ずさるすわん。 なんとなく、ここしばらくで一番のピンチって感じがした。 七
まひるは父親の書斎にある、モニター一体型のパソコンを前にして、難しい顔をしていた。 画面には、まるもじフォントで入力されたテキストファイルがワープロソフトで開かれており、まひるはそのファイルの最後に新しい文章を追加するため、マウスと人差し指を駆使してローマ字入力をしている。 そのファイルは、ここ二ヶ月の《猫と狩人》の活動の詳細が記録されている。 実際、まひるは困っていた。 状況がことごとく、まひるの予想を裏切っているのだ。 まず最初に、 彼女はなぜ、自分が街中で超級幻我を持っていたかという疑問に気づいていない。 あの場所にすわんが剣を持って立っていたのが偶然ではなく、精神を調節された結果であることを、彼女はまだ自覚してはいない。剣に宿る半多重 そのくせ、いきなり信じられない能力を引き出してみせたりする。思い込みが激しい そして翌日、気をとり直して当初の計画どおり、いや急遽対戦カードを変更し、ずっと後にぶつけるはずの 技術や経験をいえば、 もとから潜在的な総量が違いすぎるのである。少しでもその気になれば、多少の技量差などパワーで押し切ってしまうのだ。 本気になったすわんの恐さは、理解しているつもりだった。だからこそ、二ヶ月間もすわんと関わることを禁じ、こちらの個人能力の低さを技術や経験で補い、つねにイイ まひるには、今すぐすわんを倒すつもりはない。今レベルの実力なら、すわんはまひるの足もとにも及ばないのは明らかだ。だが、いずれはすわんにも、まひると同等以上の実力を身につけてもらわねばならない。 そのためにも、すわんの実力を引き出せる強力な──だが対戦時のすわんのには一歩劣る──やられ役が、どうしても必要だったのだ。 そんな内容のレポートを、まひるなりの文章でまとめながら、ふぅーっと息をはく。 やっぱり、自分一人で考えるのには限界があるな、まひるはそう思っていた。 いつまでもこんな綱渡りを続けて行けば、いずれ計画に致命的な問題が生じるのは目に見えている。 だが彼女には、これからどうすべきかという最善を見定めることができない。組織の長として全体を把握し、将来を見定め、人材を効率よく運用するということは、十三歳のまひるだけではどうしても無理があるのだ。 理由はわかっている。まひるを いくら知識があっても、樺良がまひるに知識を与えた段階では考えていなかった問題に、樺良の知識は答えてはくれない。 まひるにはまひるのスタイルがあるはずだ。要は《猫と狩人》の最終目標『 そして、これ以上一人で組織を運営していくことは無理である、というのがまひるの結論だった。彼女は再びタイプを再開し、今後の方針をまとめ始めた。 ではどうするか? だが誰を?今いるメンバーの中からか?それとも新たに誰かを調節するのか? 裏切らないからといって、正しい判断ができるとは限らない。 ここはやはり、信頼できる大人に相談役を任せたいと、まひるは思うのだ。 子供は大人を信用しないものである。まひるにも、そんな大人への不信感がないわけではない。だが、他人の思考が読める彼女には、大人が普段、どんなことを考えて生きているか知ることができる。それは、思春期の少女には、あまりにえげつないものではあったが、 そんなまひるから見て、まとまった考えができるのはやっぱり大人なのである。想像力ではなく、経験でものを判断できるのはやはり強みなのだ。 現在も、年上のメンバーは何人かいる。たが、いずれも戦闘能力重視で、頭脳労働は期待できない。やっぱり新たに参謀役として優秀な、そしていつでも相談できる立場にいる部下が必要なのだ。 最初にまひるの頭に浮かんだのは、谷々樺良である。だがその考えを、まひるはすぐに打ち消した。 それは、まひるが今の立場に立つ原因となったとか、猫耳ラブはイヤとかいう個人的な理由ではない。樺良には、樺良の役割というものがある。彼にはすわん側にいてもらわねばならない。精神的に自由なままで。 それからまひるは、参謀役になりそうな候補者リストを作成し、最後にこう締めくくった。 『このなかからまず一人、一番たよりになりそうな人に仲間になってもらいます。それから、その人と相談して、あと2、3人仲間になってもらう人を決めます。この人たちは、まひるとおなじだけの知識をもっていますが、闘う力はまったくありません。その人たちにこれからのことを考えてもらい、まひるがそれをホントにやるか決めます。これでまひるは、まひるにしかできないことを、ガンバれます』 そこまでタイプしてからァイルを上書き保存すると、ワープロソフトを終了した。 画面はグレー地のシンプルなものになり、そこにいくつかのアイコンとウインドウが並んでいる。 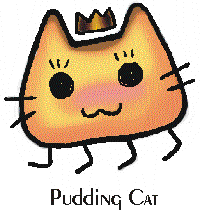 まひるはその中から『プリンねこ』と書かれたアイコンをマウスでつかみ、ごみ箱と書かれたアイコンに重ねる。
まひるはその中から『プリンねこ』と書かれたアイコンをマウスでつかみ、ごみ箱と書かれたアイコンに重ねる。
すると、モニターの下にある横長の穴から、しゃこっとフロッピーディスクが吐き出された。 ディスクのラベルには、さきほどアイコンになっていたのと同じキャラクターが大きくプリントアウトされている。それは、耳つきプリンに黒線で猫の目と鼻とヒゲ、底に四本の足が生えているというかんじの、ちょっとおいしそうなキャラクター、これが『プリンねこ』である まひるとしては、《猫と狩人》のマスコットキャラクターのつもりで、反抗声明などに印刷したりしてみたのだが、イマイチ世間の関心は低い。てゆうか、《猫と狩人》の社員の中ですら、認知度はないに等しい。 こういうことを マウスで画面の中からシステム終了を選び、フロッピーをプラプラさせながら部屋を後にするまひる。 しばらくハードディスクを検査していたリンゴマークのパソコンは、彼女が明かりを消し、父親の部屋を出るのと同時に電源を切った。 |

Copyright(c) 2000 Astronaut by Ikuo/Yoshitake